ブリッカ著 ピアノスコア『ウィリアム・シェイクスピア』の序文
デンマーク音楽出版協会(1873年)
ブリッカ(Bricka, Georg Stephan, 1842—1901)のクーラウ作曲『ウイリアム・シェークスピア』ピアノスコア(1873年出版)の序文「Fr.クーラウについての記述」は音楽史上クーラウ研究の先鞭をつけたものです。会報16号に掲載したブリッカの「いろいろな人々からの口頭の報告を集めたフリードリヒ・クーラウについての覚え書き」がこの序文の基礎となり多数引用されていることがおわかりいただけることと思います。翌年の1874年にトラーネの「クーラウ伝記」が出版されましたが、彼はブリッカの「覚え書き」、「序文」を大いに参考にした跡が見られます。ブリッカの記述はその後の研究によって、誤記と見られる個所があるとは言え、クーラウ研究のパイオニアとして重要な働きをした人です。なお、訳文中の人名、地名など固有名のカナ表記は、新谷俊裕・大辺理恵・間瀬英夫『デンマーク語固有名詞カナ表記小辞典(IDUN -北欧研究-別冊2号)』(大阪大学世界言語研究センター:デンマーク語・スウェーデン語研究室、2009年)を参考にしています。翻訳者:奥山裕介氏の紹介は翻訳文の最後に掲載しています。
(石原利矩・記)
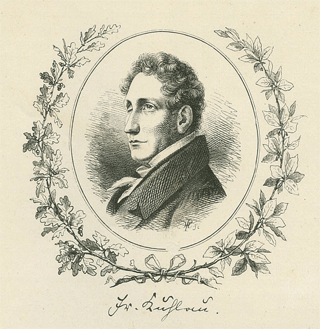 |
Fr.クーラウ
1811年1月23日、コペンハーゲンの王立劇場で演奏会が行われました。そこに登場した外国人芸術家についてはわずかなことしか知られておらず、ただ彼の名前は人の知るところであったと考えられ、故郷の町から亡命してデンマークにやって来たといわれていました。しかしヨーロッパで得た名声は、彼の登場に箔をつけはしませんでした。幕が上がると黒い衣装をまとったがっしりした姿が少し角ばってみえる、背の高い若者が現れました。彼は強い巻き毛で赤みを帯びた大きな顔で、右目が失われていることで損なわれた風貌をしていましたが、それ以外は身ごなしにあらわれた明らかな不器用さともやや対照的なおおらかな率直な印象を与えました。つまり、ある種の外見の調和が失われていたのです。彼はピアノの前に座り、指揮者のクンツェンが指揮棒を挙げ、ピアノ協奏曲ハ長調が始まりました。するとそれまで彼にまつわりついていたぎこちなさが消えました。楽音が手のもとで生まれ、指がおどろくべき卓越さで鍵盤の上を駆け巡るとき、巨匠の真面目が現れたのです。最後のアレグロを弾き終わりピアノから立ち上がったとき、フリードリヒ・クーラウは初めてデンマークの聴衆の喝采を受けたのでした。
フレゼリク・デーニエル・ルードルフ・クーラウは1786年9月11日、リューネブルクから東南5マイルにある小さな町、ユルツェンで生まれました。彼が生まれたのは貧しい境遇で、将来の展望も乏しいものでした。父親ヨハン・カール・クーラウはハノーファー連隊のオーボエ奏者でフレゼリク以外に2人の息子と3人の娘からなる大勢の子供を養わなければなりませんでした。それゆえ、彼が子供の養育に注ぐことのできた配慮は、彼自身が粗野で無教養な人間であったことも手伝って、みるべきほどのものではありませんでした。それに反して母親は教養のある婦人でフレゼリクは彼女の最期の日々まで類い稀な献身を尽くし、彼女は彼に強い影響力を持っていました。両親は彼が7歳の頃リューネブルクに移住しました。ここで彼の運命は予想もしない形で決定しました。すでに父親はフレゼリクに特に音楽の道に進めようとしたわけでなく音楽の手ほどきを施していました。母親から買い物の使いに出されたある晩、彼は暗い道で転び、階段の角で右目を強く打ちました。家に連れ帰られると、呼ばれた医者は片目を残すにはもう片方の目を摘出しなければならないと告げました。長い療養の気晴らしに、彼はベッドの向かいに鍵盤楽器を置いてもらいました。絶えず演奏したことにより彼の音楽的才能が目覚めたので、両親はこのことに目をつけ、息子の才能を利用して彼の将来を確かなものにしようと決心しました。彼は、その地に住むアーレンボステルという名のオルガニストを教師としてつけられ、ピアノ演奏の指導を受けました。父はみずから彼にフルートの吹き方を教えました。そして彼は両方に長足の進歩を見せました。それだけではありません。未来の作曲家は、すでにその片鱗を現していました。生徒の時分から彼は、フルートを奏する薬種商のために小品を書くことによって、彼のところで干し葡萄とアーモンドにありついていたと思われます。それらの小品を、彼は父のために出版しました[訳注:出版の事実は記録にありません]。やがてまもなく、ふたりの指導者が導くことができた分にもまして、彼の才能はさらに進歩しました。彼の幸福のために両親は、しかるべき教育を受けるだけの資金を与える努力をしなければならないとわかっていました。
その頃C. F. G. シュヴェンケはハンブルクのカタリーネ教会の音楽監督でした。彼は若くしてC. Ph. エマヌエル・バッハの後継者となった人で卓越した教育的音楽家でした。さらに彼は己の専門以外の複数の方面でも素養を身につけました。もしかしたらクーラウがハンブルクに送られ、シュヴェンケに師事したのは、たびたびいわれるような偶発的な事情のしからしむるところだったのかもしれません。それについては皆目わかりません。ハンブルクに赴かなければ、彼はデンマークに渡ることもまずなかったでしょう。クーラウを無償で教えたシュヴェンケはこの才能豊かな弟子を賞賛し、彼について、「情感と悟性の両面で根っからの音楽家気質である」と発言しています。しかし、昔の学校教師によくあることですが、彼は弟子に対して、若い翼が力強く広がり始めているのも構わず、まったくの子供として語りかけ、取り扱いました。それゆえ後年クーラウは、私たちには秘されてきた彼の青年時代のごくわずかな痕跡のひとつである情景を、一種の満足とともに回想しています。ある日シュヴェンケの部屋で彼の帰りを待っていたときのこと、師のパイプのひとつで勝手にタバコを吸っていました。シュヴェンケが家に帰ってきたときに、のっぽの片目のクーラウを毛嫌いしていた彼の娘から、弟子がしていたことを聞くと、彼は不快に満ちた様子で部屋に入ってきて、おびただしい叱責の言葉を浴びせました。弟子はその言葉を打ちひしがれた様子で聞いていました。そして師は、いっそう苦り切った様子で、クーラウが持ってきた作品である一冊のノートを彼の手から取り上げ、中を読み始めました。ところが、読んでいるうちに怒りが静まり、通読したところで彼は言いました。「クーラウさん、パイプにタバコをお詰めなさい」。クーラウがこの逸話を物語ると、これが自分の人生でもっとも光栄ある瞬間だったと好んで言ったものでした。このエピソードは、師弟の性格をそれぞれに特徴づけるのに役立ちます。クーラウにとって、これは彼の創作の卓越性の証明でした。けれども彼は、もてるかぎりの精力と根気で努力することもしていて、長足の進歩を遂げました。彼は主として独習でしたが、ピアノ演奏ではあらゆる面で名人の名に恥じぬ完璧性に到達しました。多くの他の楽器もよく練習し、四重奏[訳注:弦楽四重奏のことと思われるが、どの楽器を担当したかは不明]その他に参加して演奏することができるほどでした。理論でも彼は、シュヴェンケの指導のおかげで、若年にしてすでに押しも押されもせぬ博識の音楽家となるほどの進歩をみせていました。こういったあれこれの研究が、彼の時間の大部分を占めていましたが、ピアノ演奏の知識によって衣食の用を足す基盤を整えるのに十分でもありました。しかし、このほかにも彼は、ハンブルクで開かれる愛好家コンサートで実際的な役割を果たさなければならず、ハンブルクとアルトナで出版される歌曲、ピアノ曲、フルート曲、弦楽のそれぞれにわたって、おびただしい数の曲を書かねばなりませんでした。これらの作曲の大部分が、のちに彼みずから若年の作として作品群から除外した駄作にとどまらないものであるならば、彼の中で創作欲が生き生きと湧き起こっていて、諸々の事情が彼にとって順調に運んでさえいれば、それらは将来に対してまた違った、よりよい結果を期待できたことの証になるでしょう。
このことは、ナポレオンがその夏、オランダをみずからの直接支配のもとに組み込み、大陸封鎖を完成させるためにドイツ北海岸の征圧に従事していたという、またしても一見したところ偶然によって起こりました。クーラウは、フランス兵に徴発される恐れがあると悟り、そのためハンブルクから脱出する決心をしました。1810年の末、彼はコペンハーゲンに渡り、その地で最初のうちはなお捜索の手を恐れながら身を潜めていました。そうしているかぎりなんら危険は及ばず、異国の街で暮らしていくには自分への注目を惹きつけることにこそ努力しなければなりませんでした。1811年に、彼は王立劇場でふたつの演奏会を催し、みずからの演奏によって聴衆の賛嘆を呼び起こしました。他面それは、我々の時代におけるような大掛かりで絢爛たる演出ではなく、むしろ私たちが今では小演奏と呼ぶであろう、優しく上品に心を動かしはしても迫力を欠くものでした。それに対して、彼が楽譜から音を奏するときの卓越性は驚くべきもので、世に隠れなき評判をとりました。そのようにして彼は、たちまち並み外れて卓越した名人として人口に膾炙するところとなりました。1811年の暮れごろ、彼は王妃の御前で演奏するよう命じられました。枢密顧問官、のちの宮中顧問官であるブルーン家をはじめとして、当時の貴顕や芸術愛好家の家庭の多くは彼を歓迎しました。そのブルーン家で、彼はなおしばらく自由な住まいが得られ、娘のイーダが社交の場で歌うときに彼女の伴奏を務める義務から解放されました。しかし、クーラウはそのような依存状態に我慢できず、ある日前触れもなく逐電したことにより、この滞在はたいへん短いものに終わりました。全体として、その好意により宮廷楽師の称号を彼に授けた宮廷も(1813年。ただし、規定により5年後にはじめて報酬支給)、彼がはじめのころ交際していた裕福で高貴な身分の仲間も、彼を引き止めることはできず、外的状況の力だけが、彼を気の進まない、いたって不向きな交友関係に引き込みました。彼は、野卑な生家から離れたあと、独力で自己教育をしなければならなかった朴直な男でした。彼の偏狭さのために、人づきあいの接触点はわずかしか得られず、そのような影響に対する彼の受容は乏しいものでした。窮境が彼を無為に追いやり、彼の独立心はみずからの性向にしたがって結ばなければならなかった絆に反する方向へと動きました。若いころから寛大さと非の打ち所がない才能の両面でこのような関係を結んでいたヴァイセは、彼に対する強い反感を抱いていました。この対立を目の前にして、エーレンスレーヤは『回想録』の中で、クーラウの性格について次のような言葉を綴っています。「彼は異国の言葉にも学問にも身を捧げはしなかった。彼は自らの杯でワインを飲み、自らのパイプでタバコをふかした。博識の音楽家であり、美しい音楽を作曲した」と。この叙述は、ある意味で真実ではありますが、うかつにも提示の誤りを犯しています。クーラウはけっして粗野でも無教養でもありませんでした。彼は文芸を愛し、たえずデンマーク語とドイツ語で第一級の詩作品を読んでいました(というのは、彼がデンマーク語を解さないことはたびたび言明していたとおり根も葉もないことでしたが、会話練習をすることはたしかにありませんでしたから)。彼は自然に対する豊かな感性を有していて、そのため、のちにルングビューに完全に転居するまでは郊外に暮らすことを好みました。なによりもまず、彼は心の教養を有していて、友人として信実であり、教師として魅力に富んでおり、息子としては愛らしく、すすんで一族の支えとなりました。エーレンスレーヤのいうとおり、彼は容貌に恵まれず、端麗というよりは頑健な体躯をしていました。しかし、健康そうな顔のうちとけた気色と、とりわけ片側だけ残された眼のきらきらしたすばらしい表情は、彼を知るすべての人々によって記憶されています。後年、雪のように白い亜麻のスカーフを首にゆるく結び、バスローブに身をつつんだ部屋着姿の彼は、この上なく見栄えがよかったといいます*)。*)原注:彼の姿は、下に書かれた「バッハ」の名にちなむアナグラムの入った有名な石版画に描かれています。先に掲げた絵(訳注:この序文の冒頭にあるイラストのこと)は、C.ホーネマンによって先に完成されたパステル画の肖像画の一枚を元に彫られたものです。
そのような男が、フレゼリケ・ブルーンの社交場では見るからに馴染んでいませんでした。彼が居心地悪く感じる集まりから身を遠ざけたのは、なんら驚くべきことではありません。これら最初の知己のうちごく少数の者とのみ、彼は関係を継続しました。この中には、とりわけルーヴェンスキョル家の人々が含まれています。この一家の中で、彼はのちに、少年時代からすでに現われていた若きヘアマン・セヴェリンの偉大な音楽的才能を見出し、芸術の道のりにはじめて歩みだすよう導く機会を得たのです。また、クリスチャン王子とも、彼は絶えず友情に満ちた関係を保ち、典礼による制約から解放されたときは彼を頻繁に訪れました。
2年も経つうちに、クーラウはすでに傑出したピアノの巨匠として、また、とりわけはじめて評判を呼んだコンサートにより、様々なピアノフォルテ曲の才能ある作曲者として知られることとなりました。しかし、彼の才能の全体を判断する機会は、エーレンスレーヤが『盗賊の城』のテクストを書き、彼が1813年のルーヴェンボーでの4ヶ月にわたる夏季滞在中に曲をつけ、1814年5月26日に初演されて大方の喝采を受けたとき、はじめて巡ってきました。それは、この地で聴くことのできるものとしては新奇なものでした。特徴的でエネルギッシュで、どこかしら半音階のその音楽は、クンツェンの好ましくはあるがやや柔弱なメロディの豊穣さにも、はたまたヴァイセの大掛かりで深遠ながらそれゆえ大勢の聴衆を感動させる力に乏しい思想の充溢にも似ていませんでした。彼の初期の楽劇的創作を真っ先に際立たせる輝かしい器楽法は、若い作曲家たちの間に、そのような観点ではあまり馴染みのなかった舞台で驚嘆を呼び起こしました。しかし、そのようにただちに公衆の好感を勝ち得る一方で、支配的な楽派から彼に対して反発が起こりました。というのも、クーラウがいたく敬仰していたケルビーニの音楽は、彼の創作に少なからぬ影響を及ぼしていたのですが、クンツェン、C.シャルや多数の人々はこれに好意をもたなかったからです。クンツェンはなお、『盗賊の城』の音楽には許容できないほどこの楽派の影響の跡がみられることを示唆することも忘れていません。クーラウは、温厚な性情にもかかわらずこの糾弾に憤慨し、「ああ、ケルビーニの音楽もまた半音階が多すぎるではないか」という言葉で始まり、クンツェンの旋律が口笛で奏されて終わるコミック・カノンの機智に富んだやり方で返報しました。一方で、クーラウの名声はいまや不動のものとなり、一時コペンハーゲンに滞在するという彼が2年前に下した決断は、この地に永住しようという考えに徐々に移行していきました。ただちに彼は、新しいドラマ仕立ての作曲にとりかかりました。それが、バゲセンがテクストを書いた『魔法の竪琴』です(1817年1月30日初演)。しかし、彼はごくささやかな好評を得たに過ぎませんでした。なぜなら、バゲセンに対する反発が、この作品の再演に際して(初演時は国王が観覧していました)、お馴染みの劇場のスペクタクルを引き起こしたからです。それらが音楽で好評を博したクーラウに対して向けられたものではないにせよ、作品が顧みられることなく、1819年に3回目の上演の試みも同様に険悪な受け取り方をされた後は、ながらく舞台から姿を消しました。
クーラウは1810年にハンブルクを去るより前に、すでにシュヴェンケの仲立ちにより、ライプツィヒの有名なブライトコプフ&ヘルテル社との結びつきを得ていました。ハンブルクのクランツ、コペンハーゲンのローセのもとでと同様に、デンマーク到着から経過した年月のうちに、彼の手で大量の曲が出版されました。その大半はピアノフォルテでしたが、歌曲やフルート曲もありました。後者の楽器には、何らかの愛着も手伝ってか、またとりわけ当時は流行の楽器であったため、フルート独奏からフルート四重奏にいたるまで、全体として多数の曲が書かれました。このような状況が、クーラウが宮廷楽団のフルート奏者であったという思い込みを引き起こす契機となっていました。しかし、これは誤りで、これらの作品のうち相当数は、彼がただの一度も自分で演奏することのできなかったものでした。作曲家として、(ピアノ演奏と音楽理論での)教師としての多大な努力により、彼はようやく安定した地位に就いていました。くわえて、彼は1818年に宮廷楽師としての俸給を認められるに至り、宮廷の用に供する荘厳な機会音楽や劇場向けの声楽曲を毎年作曲する義務に対して年間300リースデールが支給されました(のちに規定が変わり、彼は隔年で上記の作品を提出するよう義務づけられることとなりました)。彼はこのとき、この国にとどまる決意を固めることができたのでした。この決心がついたとき、彼は家族を自分のもとに呼び寄せました。彼らにつづいて、それまで両親に代わって家を率いてきた妹のマグダレーネがやってきて、弟の家庭でも同様の地位を占めました。しかし、かたや彼女はそれまでとは勝手の違う状況にどう適応してよいのかわからず、かたやクーラウはといえば、実務や経済にはとんと不向きでした。そのため、彼はたえず金銭的な窮迫の中にあり、簡単に売り上げを見込めるようなものを作曲することでそれを塞ごうとしなければならなくなりました。これにより、親しまれてきたオペラや有名な国民的・民族的旋律の主題に対する多くのピアノフォルテの変奏曲が生まれました。それらは、音楽的な価値はさして高くないものの、かつてさんざん表現されたことを小細工に走ることなく新しい手法で表現することのできる彼の汲みつくせぬ創意の証となりました。創作に打ち込んでいるときの偉大な軽快さと忍耐づよさが、彼の助けとなりました。彼はミューズの到来を待つ必要はなく、彼女と待ち合わせをするといったところでした。毎日、彼は朝から2時まで仕事をしました。午後に執筆することはまずなくて、着想が湧いたときすぐに紙の上に書きつけられるよう、夜中に起きていました。彼が仕事を進める速さもまた、たいへんなものでした。たとえば、ピアノのためのソナチネ・ハ長調 Op.88の4曲は、その当時、『フーゴーとアデルハイド』に取り掛かっていて、まったく異なる方面の創作に支障をきたすにちがいないと思われたであろうにもかかわらず、土曜日から日曜日にかけて、午後と朝の間に書かれたものです。しかし、彼は相当な集中力を有していて、オペラ作品を編曲しなければならないときは、友人と居並んで喋り、質問し、答え、他の者が彼に出来事を語っているあいだも、休む暇なくペンを走らせている姿がみられました。
上記のとおり、宮廷楽師として俸給とともに、彼は劇場のために作曲する義務を引き継いでいました。そのため彼には、ほどなくしてオペラのテクストが届けられました。それは、ボイイによって作られた『エリサ』で、1820年4月1日に上演されました。この作品につけられた音楽は、『盗賊の城』の清新さの幾分かが欠けていなければ、実際よりもきっと良い運命に導かれてよいはずのものでした。しかし、テクストが劇性に乏しかったため、作曲家に対する聴衆の好感にもかかわらず、舞台に作品をかけることはできなくなり、ほんの数回の上演を経て、『魔法の竪琴』と同様に姿を消しました。もしかすると、これらの度重なる不運のために、彼はながらく望んでいた外国旅行を実行することに決めたのかもしれません。彼は1821年に出立し、ドイツの大都市の多くを歴訪し、多くの音楽出版業界人の知遇を得て、ウィーンからコペンハーゲンの友人に宛てて、指導をやめて作品に対する謝礼でのみ生活できる望みが出てきたと書き送りました。クーラウが旅に出ていたまさにその当時、ヴェーバーの『魔弾の射手』がドイツの舞台に現れました。ほとんど無名の名前をたちまちのうちに万人の口の端に上らせたこの不思議で独創的な曲は、クーラウの柔軟な精神に強い印象を刻まなかったはずがありません。この印象と旅によって新たな生気を得た意力を携えて、彼はデンマークに帰りました。ほどなく『ルル』のテクストが劇場から送られたとき、彼は意想と創作欲に満ち満ちて作品に取り掛かりました。それらは、彼が提出した作曲の中にありありと認められたもので、彼の精神のこのうえない表出でした。『ルル』は1824年10月29日に上演され、彼の初期作品のすべてを上回る千変万化の旋律と器楽法のきらめきに満ち満ちた演奏が行われましたが、作曲家の変更が行われたかのような決定的な印象をも与えました。そのことについては、以前にもましてメロディの充溢と旋律自体のよりやわらかで熱が通っていて歌高らかな性格を求めて貫徹された努力に支えられたものでした。ロッシーニの名は当時コペンハーゲンの大規模な楽派にとっては禁制品でした。クーラウ自身は彼の「軽薄な」音楽に対する反発をはげしく口にする人々の側に属していました。一方で、ほかならぬ彼の作品にある種の「ロッシナーデ」が見出せると思うものもいました。影響がひとりの作曲家と当時の新しい傾向に帰せられるとすれば、それはまったくちがった淵源を有していたにもかかわらず。そのようにして、5年前は『赤ずきんちゃん』がきっかけでフランス・イタリア音楽の擁護者であるシボーニに対して巻き起こった反発のための決まり文句としてヴァイセと同様にその名が槍玉に挙げられていたクーラウは、いまやこの非愛国的な趣味の信奉者として憎悪されるところとなりました。口笛を吹いてやろうと待ち構える者すらいました。クーラウが劇場に来ると、口笛が吹かれる見通しからそれを推奨するならず者からチケットが差し出されました。しかし、その試みは失敗しました。その作品は、ギュンテルベルクのテクストがかなりの上出来で、当時つくられた他の多くのデンマーク語オリジナルのオペラが顧みられることなく忘れられる頃になっても上演を重ね、我々の劇場の華となりました。
その器楽の構成-とりわけ室内楽-に生き生きとした賛嘆を捧げ、知遇を得ることをしきりに願っていたベートーヴェンとの面会をウィーンで果たした1825年夏のドイツへの小旅行のあと、彼はふたたび劇場から寄越された新しい仕事を引き受けました。それはいずれもボイイ作の『フーゴーとアデルハイド』と『ウィリアム・シェイクスピア』です。後者は、音楽的な構成がどちらかというと基本的な素地であるにとどまる作品で、作家はもともとシャルがこれを作曲するのだろうと思っていました。劇場支配人がクーラウをその任に選んだ後になって、時間と出費を節約するために、シャルの音楽の一部をバレエ『マクベス』に使おうと企てられたのでした。しかし、シャルが抵抗したため、これは断念されました。『フーゴーとアデルハイド』(1827年10月29日初演)は、はじめクーラウと類似の役職にあって宮廷と劇場のために作品を提出するという同じ職務を帯びていたヴァイセに命ぜられました。しかし、彼は劇場向きでないテクストに音楽をつけることに気乗りがしなかったので、その仕事はあれこれ抱えながらいちどきに何かを生み出せるつもりでいたクーラウに与えられ、それゆえ彼が引き継ぎました。彼の音楽はいつもと変わらずメロディアスかつ優美で、はじまりの徒弟と騎士の少年のあいだでの口争いのコミカルな特徴は優れた効果をあげました。ところが彼は、新参の入獄者に対する囚人たちのおどろおどろしい歓声をたくみに繰り返すことによってこの上ない効果を上げると踏んでいた騎士の投獄の場面で、あまりに不快な印象を観客に与え、それにより自分の上げようとした効果を「失敗させた」という咎められるところなき不運に見舞われたのでした。しかし、そのとおりではなかったとはいえ、作品は多大な作劇上の瑕疵によってほとんど上演を続行することはかなわなくなり、クーラウはふたたび優れた作曲が拙劣なテクストによって殺されるのをみる悲しみを味わいました。その代償は、翌年ハイベアの卓抜な筆が完成させることのできた祝祭劇を素材とする『妖精の丘』で得られました(1828年11月6日初演)。そこでは、劇場の3つの主要素である演劇・オペラ・バレエが、互いに調和した関係を結びつつ一体となっていました。『妖精の丘』はフレゼリク王子とヴィルヘルミーネ王女の婚儀のために書かれましたが、機会詩的作品にすぎないとはいえ、詩作の国民的なトーンと、すばらしい序曲を冠せられた美しい音楽、芸術と趣味が織り合わされた国民的メロディによって、デンマークの公衆の愛好の的となり、劇場でいまなお命脈を保っているクーラウの唯一の作品となりました。初演の数日前、クーラウは教授に任じられました。『妖精の丘』で、クーラウは主題に導かれて、国民的作曲家になるよう歩みを進めました。しかし、彼がこの道をそのまま進むことはありませんでした。いずれにせよ、音楽の中の国民的なものと国民的旋律の選択は、ある部分では、音楽向けに形成された人格の持ち主であり、とりわけ民謡(フォルケヴィーセ)に多大な関心を抱いていたハイベアとの接触に起因していました。100番目の作品であるこの曲の後にクーラウが書いたものには、彼の以前の創作のエネルギーと生命と清新さは多かれ少なかれ失われていました。これはある程度まで、彼の私的関係、身体的な衰弱、精神的な圧迫に原因がありました。1821年の最初の旅行で彼が抱き、将来はもっぱら作曲家としての活動によって、またその活動のために生きていければと口にした望みは、怪しいものに思えてきました。彼は、才能に恵まれ知識も豊かだがやや変わり者の妹が切り盛りしていた出費のかさむ家政にいまだ苦労していました。不器用で生活の実際面に向かない彼なりによりよい段取りをつけるために行った試みは、たえず失敗しました。彼の友人でありこの地に住んでいるドイツ人ハスハーゲンは、クーラウが仕事の万事につけて相談を求めていた楽器職人でしたが、結婚するべきだという、ひょっとすると唯一といってもいい実際的な助言を与えました。そこでクーラウは彼に、他人に誓う通りに言明しました。「そんなことをやっている時間はありません」。ややのちになって、彼は街の住居を引き払って、ルングビューに転居しました。ますます暗い気分が、ここ数年彼の中で横たわっていました。彼がいたって少数の人たちとのみ交際していたルングビューでの孤独な生活は、この境遇を改善する役には立ちませんでした。古い教え子や知人がコペンハーゲンから彼を訪ねてくるときのみ、彼は生気づき、街の出来事を尋ね、逸話を聞いて大いに楽しむことができました。彼が手離すことのなかった長いタバコ用パイプを膝の間に挟んで床に立てたままピアノに向かうとき、多くの愉快な事柄を聞くことができました。かつての陽快さが蘇ってくることもあったでしょう。彼は多弁になることはなく、たいていは途切れがちに短く早口に言葉を継ぎました。話が音楽の問題に及ぶと、彼は言葉数が多くなりました。他の作曲家に関する彼の評価は、シュポアの音楽へのコメントにみられるように、ときおりその短さに特徴を示したようです。「煮ても焼いても食えないね」。このときを除いて、彼はそのような発言をする際は、舌鋒鋭いというよりは、ほとんどいつも温厚で、憤るよりはむしろ黙っていました。彼があまり好まなかったC.シャルについてだけは、クーラウの辛辣な評価はいつも通りでした。シャルがクンツェンの死後に楽長に就任した当時、彼は次のように言っていました。「彼は8小節の音楽も正しく書けないやつだ」。しかし当時、「ああ、鼻の中の鼻」というカノンの中でクンツェンを嘲笑したときと変わらず、クーラウはまだ若かったのです。年月の流れとともに、彼は温厚になりました。ヴァイセとはあまり馬が合わない上に、ふたりは音楽的な方向やその他の人柄でもあまりに異なっていました。しかし、クーラウはヴァイセの尊大な身ぶりを高く評価していました。ヴァイセは、クーラウにみられるいくつかの側面、とりわけ独自の重要性をもっていた劇音楽作曲家としての面を評価するだけの見識もありました。彼はかつて『盗賊の城』にふれて、第1幕のアイマールとカミロの間で歌われるような二重唱を書ける作曲家はドイツにいないと弟子の前で発言しました。しかし、音楽界では、ふたりの作曲家の周りに信奉者の党派が群れをなし、各党派の立場は当の彼らにありもしない敵対関係の様相を強いたのでした。---たゆみのない努力によって、クーラウは後年作曲を続けることができました。彼は出版された分よりはるかに多くの作品を書きました。しばしば彼は、もういちど大作のオペラを書けるようになりたいという願いを口にしています。このことが、彼の最後の上演作品となった『ダマスクス生まれの三兄弟』(1830年9月2日初演)の音楽が、滑稽劇の装飾には不釣り合いなほどあまりに重々しく奇抜なものになった原因なのでしょう。たしかに、彼は年老いてはいませんでした。それでも、彼の手からあまり美しいものが作られることは期待されていませんでした。しかし、誰が示唆したわけでもなく、彼はすでに人生の幕引きにみるみる近づいていました。1830年という年は、その点で彼の運命を決定づけました。この年、彼の両親はふたりとも没しました。ふたりとの別れ、とくに母の死は、彼の心を深くえぐりました。しかし、ルングビューの住まいで火災が発生し、そのような場合には珍しくない惑乱に襲われ、消しゴムと鉛筆を猫とともに救い出しはしたものの、多年の仕事の成果である彼の膨大な草稿群が焼け果てて烏有に帰したことで、いっそう厳しい打撃が彼をうちのめしました。これによって彼がこうむった経済的な損失を、多くの人々が様々な方法で援助しようと奔走しました。ヴァイセは彼のためにコンサートを企画しました。クリスチャン王子は城中に住居を用意しましたが、こちらは彼が拒みました。しかし、彼が曲の焼亡で味わった喪失は、あがなうことのできないものでした。この悲しみは彼の精神力を完膚なきまでに打ちのめしました。以前から弱っていた彼の健康はいっそう衰えました。1831年の末、彼はフレゼリク病院に入院し、1832年3月12日にここで亡くなりました。[訳注:息を引き取った場所はニューハウンの23番地]彼の葬儀はおもに王立劇場の職員や楽団、クーラウが上級会員であった学士協会の構成員からなる多人数の参列者によって執り行われました。クリスチャン・ヴィンタのテクストに寄せたヴァイセの感動的な葬送曲が教会で斉唱され、近衛楽団は教会の外でクーラウ自身がクリスチャン7世の葬儀のさいに作曲した葬送行進曲を演奏しました。
クーラウは、新しい道を切り開く独創的な才能に恵まれた芸術家には含まれなかったでしょう。しかし、彼の徹底性と趣味が彼を逸脱や奇矯に走らせぬよう引き止める一方で、なみなみならぬ向上心を有していた彼は、時代がもたらす新しいものを、どれといわず容易に身につけました。彼とヴァイセの懸隔は、これがために生じたのです。なぜなら、こちらは一貫して変わらないのに対し、クーラウの音楽はご存知のとおりたびたび変化したのですから。しかし、彼は決して物真似屋ではありませんでした。むしろ、彼が何らかの模範に従ったというよりも、変転めまぐるしい方向をもった時代が彼に変化を促したといわなければなりません。しかし、彼に起こったそのような変化をあとづけることができるからこそ、かえってクーラウは全作品におけると同様に、基本の素質においても自分自身であり続けたのです。彼の真骨頂は、対位法的な要素です。彼の最小の作品ですら、たやすくオーケストレーションできるほど、どこかしら交響曲めいたところをもっています。彼の多声曲では、個々の声部が一定の独立性を保っています。彼はこのとおり教会作曲家になるための基本条件を満たしていましたが、そのためには彼は情緒が欠けていました。荘厳、悲愴、深く霊魂に迫る切実さが、彼には備わっていなかったのです。かわりに、魂のあらゆる軽妙な気分を表現する力を彼は有していました。生気に富んで特徴的で優美な旋律、彼が書いたあらゆるものの中でもおどろくべき歌と楽音は、ごくささやかな小品にも興味を添えました。彼の作曲は、短い生涯のわりに膨大な数を誇ります。作品数はおよそ150にのぼります。しかし、それ以外にも作品番号のない相当数の小品があり、1810年以前の若年期の作品の数は、この中には含まれていません。彼の作品はさまざまな場所で出版されましたので、彼が書いたものをもれなく一覧することは困難です。相当な数が今ではたいへん貴重なのです。良質でも完全とは言えない集成であれば、かの巨大な王立図書館が所蔵しています。劇音楽作曲家として、クーラウはたしかに偉大な名声に値しますが、彼の比較的小規模な作品のうちにも、五重奏や四重奏、ピアノ曲のような多くの優れたものがみられ、これらのうち最後のものは、レッスン曲としても有用です。ピアノ曲とフルート曲は、クーラウの名をもっとも外国で高からしめたものです。フランスでは、彼は「フルートの巨匠」と呼ばれました。ついに彼の多くの傑出した歌曲、とりわけ男声四重唱は特筆に値します。まったく独自の位置を、独特でときにグロテスクなおかしみを備えた彼のコミック・カノンは占めています。理論家としての彼の偉大な徹底性は、芸術の峻厳な領域において、多くの若い音楽家が彼の指導を求める機縁となりました。これら彼の弟子筋のうち少なからぬ人たちがなお存命で、今は亡き愛と慈しみにあふれた旧師を偲んでいます。ここに叙した記録の大部分は、彼らからの伝え聞きにもとづくものです。
ゲオ・ステファン・ブリッカ
翻訳:奥山 裕介(IFKS会員:379)
大阪大学大学院文学研究科博士後期課程在学。平成24年度日本学術振興会特別研究員に採用。専門は近代デンマーク文学および北欧地域文化論。主要業績は、論文「跳躍の条件としての不安 ― カーアン・ブリクセン『詩人』における楽園追放の想起と反復」(『世界文学』第123号、2016年)、「ヘアマン・バング『化粧漆喰』におけるシュレースヴィヒ戦争の記憶 ― 1880年代コペンハーゲンの娯楽スペクタクル文化と北欧地域像の関係」(『比較文化研究』第102号、比較文化学会、2013年)、「歓楽のディアレクティク ― 都市コペンハーゲンにおけるティヴォリ遊園と群衆の表象」(『独文学報』第27号、大阪大学ドイツ文学会、2011年)、「J. P. ヤコプスン『ニルス・リューネ』における「例外者」 ―〈アラディン型〉人物類型の変成史との関係から」(『独文学報』第26号、大阪大学ドイツ文学会、2010年)など。